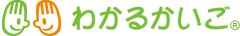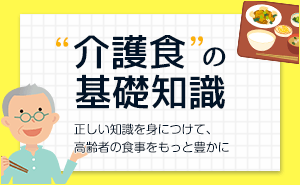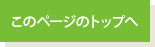知っておきたい基礎知識(認知症行動・介護便利グッズ)
■介護の基礎知識
気をつけたい高齢者の病気・怪我 | 成年後見人制度について | 在宅介護を行う際の留意点(食事・排泄・入浴など)| 知っておきたい基礎知識(認知症行動・介護便利グッズ)
知っておきたい基礎知識(認知症行動・介護便利グッズ)
●認知症行動

『認知症』とは
脳や身体の疾患を原因として、記憶・判断力などの障害がおこり、普通の社会生活がおくれなくなった状態と定義されています。
認知症の初期症状で最も多いのは「もの忘れ」ですが、意欲、自発性の低下(やる気がおこらない、これまでやっていた事をしなくなった、ものぐさになった)やうつ症状、言葉の障害、注意力低下なども認知症の初期症状として現れることがあります。
また、認知症の発症のきっかけとなるものは以下のものがあります。
- 環境の変化
- 不安・心配ごと
- 自信や役割意識の喪失
生活上で心当たりがあったら、初期症状が出ていないか注意深く観察しましょう。
【初期における対応・進行を防ぐ方法】

- 理解力や記憶力の低下はご本人自身が感じている場合が多く、過度に不安にさせないことが重要です。できないことを責めたり叱ったりせず、まだできることに目を向けましょう。
- 閉じこもりがちにならず、積極的に外出し、社会との接点をもちましょう。
- 適度な運動や新しいことへのチャレンジ、指先を動かす行動などは、認知症予防に効果があるといわれています。道筋を立てて考える行動(旅行の計画や料理など)も、脳を刺激し認知症予防に取り入れられています。
- ○認知症の症状
- 認知症の症状は、中核症状(必ずみられる症状)と、周辺症状(必ずみられるとは限らない症状)に分けられます。
- <中核症状>
-
- 記憶障害(ついさっきのことを忘れる、新しいことを覚えられない)
- 見当識障害(日付や場所がわからない、他者との関係がわからない)
- 判断力の低下(順序だてて行う料理などができなくなるなど)
- 失語(言葉がでない、理解できない)
- 失認・失行(知っているはずのこと・できるはずの行動がわからなくなる)
- <周辺症状>
-

- 幻覚や妄想(もの盗られ妄想など)
しまい忘れた財布や通帳を誰かが盗んだ、自分に嫌がらせをするために隠したという「もの盗られ妄想」は、最も身近な家族が対象になることが多いです。この他に「嫁がごはんに毒を入れている」という被害妄想や、「主人の所に女が来ている」といった嫉妬妄想などということもあります。
- 物事への執着・収集行動
好きなものや執着しているものを大事にしまい、引き出しやベッドの下から新聞などが大量に出てきたり、カビの生えたお饅頭が出てきたりします。
- 過食・異食
食事をしても「お腹がすいた」と訴えるたり、食べられないもの(ティッシュペーパー、石けんなど)を口に入れる異食がみられることがあります。
- 暴言・暴力や介護への抵抗
特に、行動を注意・制止する時に起きやすく、型にはめようとすることで不満が爆発するということが少なくありません。また、幻覚や妄想から二次的に生じる場合もあります。介護への抵抗は入浴を嫌がることが多く、「明日はいる」「風邪をひいている」などと口実をつけ、介護に抵抗します。
- 徘徊(帰宅願望など)
自分の家への道など当然知っているはずの場所で迷い、行方不明になったりします。また、自宅にいるのに「帰ります」と言って外に出てしまうこともあります。
- 幻覚や妄想(もの盗られ妄想など)
- ○認知症の対応
- <認知症の方への理解と接し方>
-
- 認知症の方の脳の働きをよく理解する
- 視覚・嗅覚・味覚などの感覚も変化していることを理解する
- 認知症があっても一定範囲の日常生活を持続させる(残った機能を生かして日常生活を持続する)
- 出来なくなったことを無理やりさせない
- 自尊心を傷つけない(認知症だからと軽視したり、無視したりしない)
- <接し方の原則>
- 認知症の方の症状や行動はさまざまなものがありますが、大きく「事実の誤り(現実のとり違え)」と「失敗行動」に分けられます。 問題が起きたときにはそれぞれ原則に合わせて対応しましょう。
行動 対応の原則 事実の誤り(現実の取り違え) 財布などを盗られたと疑う
実際に存在しないものが見えたり聞こえたりする
人をとりちがえるなど
否定しないこと(逆らわない) 話題・場面をかえ、関心をそらせる
認知症の方の認識に合わす
否定しないこと(逆らわない) 話題・場面をかえ、関心をそらせる
認知症の方の認識に合わす
叱らない、説得しないこと ※(禁句)「ダメじゃない」「いけません」
失敗しないような状況(環境)をつくる
行動の動機や背景を考え、それを満たす

認知症の方の対応で心がけることは、「自尊心を尊重すること」です。認知症の方を子どものように叱りつけたり、頭ごなしに否定したりすると、自尊心(プライド)が傷つけられます。
同じ話や同じ質問を何度もされるというのは、同居している方にとって、かなりのストレスになります。また、家族それぞれのペースを意図的に乱そうとしているかのように、認知症の方は介入してくるので、周囲は混乱し、感情的になる事が多くなります。
受け止める・傾聴も、余裕がなければできないことです。

認知症かな?と思ったら、受診と同様に「ご本人の外出機会を確保すること」「ご本人にできるような役割を渡すこと」に注意をおいてみてください。
ご本人にしかできない役割を渡すことで、プライドがくすぐられ、その時間集中して取り組めたり、ご本人が大事にされる環境を確保しご家族だけの時間を持つことを大事にすることで、ご本人の感情が穏やかになり、ご家族も客観的に関われるようになります。
また、体の具合が悪い時にも、乱暴な表現が出たり、落ち着かなかったりします。
熱が出ていたり、便秘でお腹がいたかったり、そのようなことが認知症の方の理解しがたい行動として現れることがあります。
認知症の方は、自分の体に起こっている不具合を表現できないことが多いです。
薬を勧められた時にも、お医者さんに薬の副作用にどんなものがあるか聞いてみてください。
なんとなく落ち着かなくなったとか、乱暴になったなど、その背景に副作用がある場合があります。
●介護便利グッズ
- ○福祉用具と日用品の選び方
- 福祉用具や日用品は、日常生活に支障がある方が、ご自身でできることを補助する用具のことです。介護保険では自立支援を目的に、レンタルや購入の制度があります。
いずれも介護保険を申請し、要支援や要介護と認定された場合のみ、1割負担で利用できます。
- ○福祉用具の主な種類
-
- ・介護用ベッド
-

寝返りや起き上がりがしにくくなったり、一日の大半をベッドですごす人には介護用ベッドは必需品です。また、介護する人にとっても、背あげや高さを変えられる電動ベッドは
身体への負担軽減に役立ちます。介護用ベッドは介護保険では原則として、要介護2以上の方にレンタルされます。マットレスやベッド柵、移動用バー、ベッドサイドテーブル、
移乗用のボードやシートなど関連する付属品もレンタル対象品です。
- ・車いす
-
 大きく分けて、自身で操作する自走用・介助してもらって移動する介助用・電動車いすの3種類があります。心身の状態や利用場所によって選ぶポイントが異なり、長時間利用する方の場合はフィッティングが
大きく分けて、自身で操作する自走用・介助してもらって移動する介助用・電動車いすの3種類があります。心身の状態や利用場所によって選ぶポイントが異なり、長時間利用する方の場合はフィッティングが
重要となるため、レンタル・購入の際には福祉用具専門相談員に相談しましょう。
- <車いすの選び方>
- 室内移動の場合、室内導線や廊下幅、出入り口の幅などのサイズが車いすに合っているかどうか、事前に計測しておきましょう。また、トイレや洗面所などの狭い空間での回転や移乗が難しい場合は、住宅改修も念頭に入れ、福祉用具専門相談員に相談しましょう。
外出用であれば、要介護高齢者の場合、基本的には押してもらうタイプの介助用車いすのほうが安全です。自走式の場合は、タイヤの口径の大きいもののほうが安定して走行できます。周辺の道路の状況を事前によく調べ、段差や横断歩道、ふみきりなど危険な場所への対策を講じましょう。
- ・ポータブルトイレ
-

トイレが間に合わない、寝室から遠いなど、排泄に不安を覚えたら、寝室にポータブルトイレの導入を検討しましょう。脱臭機能付き、家具調など種類もさまざまです。介護保険では購入対象品になっています。
- ・入浴補助具
-

高齢者の家庭内事故の多くは、浴室で起こります。安全に入浴するための入浴用いす、浴室用手すり、入浴台、すのこなどは、介護保険の購入対象品になっています。
- ・その他
-

歩行補助杖、シルバーカー、スロープ、徘徊感知機器などが介護保険のレンタル対象品になっています。介護保険適用の可否は医師や理学療法士、ケアマネジャーに相談しましょう。
- ~歩行に不安がある場合~
- 転倒の危険性があったり、一人での歩行が不安になったら車いすや歩行補助具を利用します。室内移動は手すりや歩行器があれば歩けるけれど、外で長時間移動は難しい場合は、室内では
手すりや歩行器、外では車いすなど状況に応じて使い分けます。
いずれもたくさんの種類がありますが、デザインや価格重視で選択すると、さらに身体に負担をかけてしまう場合があるため、必ず医師や理学療法士など医療の専門家や
福祉用具専門相談員に相談し、身体にフィットしたものを選ぶ必要があります。
なお、普及品のT字杖は介護保険のレンタル対象品にはなっていません。
- ○日用品・衣服選びのポイント
- 食事や着替え、排泄など、日常生活をサポートする便利な道具を自助具といいます。介護保険の対象ではありませんが、高齢者が一人でできることを手助けしてくれ、介護者の介護負担も軽減してくれる優れものが数多くあります。
- これらはデパートや大型量販店の介護用品売り場で扱っているほか、福祉用具を扱うショップにおいてあるカタログに、たくさんの種類が紹介されています。いずれも取り寄せや通信販売が可能です。100円均一のショップで扱っているところもあります。
-
- ・脱ぎきしやすい衣服
-

加齢に伴い背中が丸くなったり、まひがあって一人で着替えられない方用の、着脱しやすい衣類が販売されています。しかしこうした衣類は種類が少なく価格も高価なため、ミシンが使える方ならリフォームをおすすめします。ボタンをマジックテープに交換したり、えりぐりに切れ目を入れて広くするだけでも、格段に着がえが楽になります。
- ・リハビリシューズ
-

マジックテープ付きで着脱が簡単で、甲をしっかり固定し歩きやすいシューズが発売されています。障害のある方が補装具(足を支える道具)とともに装着することができるよう、片足ずつ販売されているものもあります。
- ・曲がりスプーン
-

握る力が弱くなったり、口まで運ぶことが難しい方のために、スプーンやフォークの柄を自由に曲げられるように工夫されています。また、柄の部分の太さを変えることで、本人の力や手の大きさに合わせることができます。
- ・滑りにくい食器
-

両手を使って食事をするのが難しい方には、食器の底が滑らないシリコンやゴム製になっていて、支えなしで箸やフォークを使っても滑らず安定している食器や、手前と奥の深さが異なり、すくいやすい器などが発売されています。
- ・口腔ケア用品
-

自分で歯磨きできなくなった方用に、刺激の少ないスポンジ球のついたブラシや、弱った歯肉を傷めずにケアするための指サック状の口腔ケア用品、口腔ケア用ウエットティッシュなどがあります。
- ○排泄用品
- 排泄は人の尊厳にかかわる部分のため、介護が必要になっても、トイレ介助やおむつ利用に抵抗を示す方は多いもの。現在は、排泄用品も便利で使いやすい高機能なものが増えているので、まずはサンプルを取り寄せるなどして、使い心地を試してもらいましょう。
- 自力で排泄できるけれど、トイレに間に合わず失禁することが多い方は、居室にポータブルトイレを置いたり、下着感覚のパンツタイプのおむつから試していただくなど、段階的に排泄用品を導入していきましょう。
-
<おむつの種類>
- ・失禁パンツ
-

くしゃみや少し力が入った時などに少量漏れてしまう方が使用することが多いです。50~100ミリくらいの漏れまでは対応でき、繰り返し使えて経済的です。
- ・パッド併用パンツ
-

ショーツの両脇が開閉できるため、オムツをはずすことに向けてパッドが取り外しでき、ご自身で交換できるタイプです。他に、前開きのものなどもあります。
- ・リハビリパンツ
-

下着のようにはけるタイプで、最近ではズボンをはくとつけていることがわからない薄型タイプのものも増えてきました。日中は自分で、夜間は介助で交換しやすいよう、ウエスト部分の左右にテープがついたタイプもあります。
- ・尿取りパッド
-

製品によって、1回~数回分吸収できるものがあります。テープ型のおむつは、尿取りパッドを併用することで、1回ごとに交換しなくても済み経済的です。
- ・テープ型おむつ
-

ベッド上で過ごされる時間が長い方がご利用する、介助者に交換してもらうタイプです。体のサイズに合ったものを選び、尿取りパッドと併用します。
- ・平おむつ
-

防水シーツの代わりにも使える、経済的なフラットタイプのおむつです。主におむつカバーと併用します。
<おむつの当て方>
もれ箇所 テープ型紙おむつ パンツ型紙おむつ 脇 1. 太もも部分に隙間ができていないか確認しましょう。 2. ウエストテープを引き上げる
ようにして止めなおすといいでしょう。
1. リハビリパンツの後ろ部分にシールが付いています。 2. 前後を反対にはくと漏れの原因になります。
腹側 1. 体の左右の中心に紙おむつを合わせます。 2. ヒップサイズを目安にサイズを確認しましょう。
3. 男性の場合、尿取りパッドを併用すると効果的です。
4. 女性の場合は尿取りパッドを蛇腹のように畳んで当てるとたくさん吸収できます。
5. 衣類や下着が紙おむつと体の間に挟まっていないか確かめましょう。
1. ウエストサイズを目安にお腹に余分な隙間ができないものを選びます。 背中 1. ウエストまわりにギャザーなどがある商品を使用し、隙間ができないように当てましょう。 2. 衣類や下着が紙おむつと体の間に挟まっているともれることがあります。
3. おなかの調子を崩し便が水様の場合には、防水シーツや平オムツを下に引いて経過を見ましょう。
1. ウエストサイズを目安にサイズを確認しましょう。 2. 衣類や下着が紙おむつと体の間に挟まっているともれることがあります。
股 1. 両足のももの付け根に沿って紙おむつを当て、足まわりのギャザーは立てて使用します。 2. おしっこが出てくる部分に紙おむつを密着させ当てます。
3. 足まわりのギャザーが外側に正しく出ているかを確認しましょう。
1. おしっこが出る部分に紙おむつを密着させるように少し腰部を引き上げましょう。 2. 尿取りパッドを使用する場合は立体ギャザーの内側にパッドがおさまるようにして使用しましょう。
気をつけたい高齢者の病気・怪我 | 成年後見人制度について | 在宅介護を行う際の留意点(食事・排泄・入浴など)| 在宅介護のポイント(2)