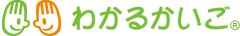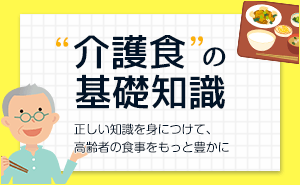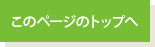介護の相談はどこにすればいい?
どこに相談すればいい?
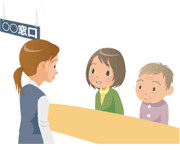
体が不自由になったり、認知症と診断されるなどで親の介護を覚悟したとき、家族だけで抱え込まないことが大切です。介護保険サービスを適切に使うためにも、地域の相談窓口を活用しましょう。
入院なのか自宅にいるのか、親元が遠隔地など、状況によって相談する場所や心構えが違うことも頭に入れておきましょう。
親の介護を覚悟したら
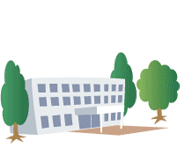
■病院に入院している場合
病院に医療ソーシャルワーカー(*1)がいれば相談する。
容態が安定したら、退院後のことを医療ソーシャルワーカーに相談しましょう。介護保険の申請のほか、地域の介護予防サービスの活用、転院や施設への入所などについてもアドバイスを求めることができます。
■自宅で介護する場合
市町村の担当課(高齢者福祉課・介護保健課など)、または地域包括支援センター(*2)に相談する。
介護保険については市町村の担当課、介護予防については地域包括支援センターが担当します。まずは介護についての情報を得たい場合、介護以外にも相談したいことがある場合は、地域包括支援センターが窓口になります。
■離れて暮らしている場合
介護が必要な家族が暮らしている市町村の担当課(高齢者福祉課・介護保健課など)、地域包括支援センターに相談する。
介護保険やその他の行政サービスを利用する場合、被介護者が住んでいる市町村が相談窓口になります。現地に出向く前に、電話で相談したりパンフレットを取り寄せるのがおすすめ。介護が必要となる前に備えておくと安心です。
(*1) 医療ソーシャルワーカー(MSW)とは
地域の保健・医療・福祉機関と連携し、患者の在宅療養の準備をサポートします。転院や施設への入所、介護保険の申請の相談にも応じてくれます。MSWを配置しているのは、総合病院、または100床以上の病院の一部です。
(*2) 地域包括支援センター
全国の市町村に配置され、介護・医療をはじめ、高齢者の生活全般についての相談窓口となります。保健師、社会福祉士、ケアマネージャーが相談業務に従事し、介護予防の拠点としても機能します。「あんしんすこやかセンター」などと名前を変えている場合もあります。
| << 親が突然倒れたときは | 「介護のキホン」トップへ | 相談可能な機関一覧 >> |